電話番号:03-5626-3242開館日・開館時間:火曜日から日曜日(午後1時30分~午後5時)休館日:月曜日(ただし、祝休日の場合は開館)
ここから本文です。
更新日:2024年10月24日
松原良水彩画展 落語ゆかりの地を描く第3弾展示作品
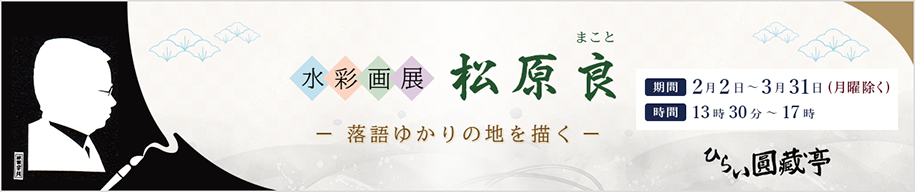
落語の舞台を描いた水彩画です。
第3弾(令和3年2月2日~3月31日)作品展示
360度カメラで水彩画展の様子を見る
江戸川画像文庫で高画質の絵を見る
第1弾作品展示を見る
第2弾作品展示を見る
お問い合わせ
電話番号:03-5626-3242開館日・開館時間:火曜日から日曜日(午後1時30分~午後5時)休館日:月曜日(ただし、祝休日の場合は開館)
ここから本文です。
更新日:2024年10月24日
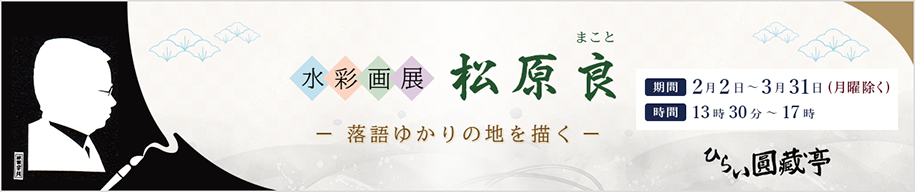
落語の舞台を描いた水彩画です。
お問い合わせ