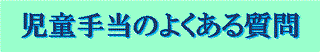更新日:2025年10月16日
ページID:7402
ここから本文です。
児童手当
(注)令和6年9月分までの児童手当については、児童手当(令和6年9月分までの制度)をご覧ください。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした、国の子育て支援策です。
窓口混雑予想と手続き時間
比較的空いている時間帯、曜日等
- 午前8時30分から午前10時まで
- 火曜日から木曜日(月末、連休前後は除く)
- 雨天の日
混雑が予想される時間帯、曜日等
- 午前11時から午後1時まで
- 午後4時から午後5時15分まで
- 月曜日または祝日明け
- 月末
- 3月、4月、5月(住民票の異動が多い時期のため)
- 8月(ひとり親手当の現況届提出月のため)
1.支給対象者
18歳到達後、最初の年度末まで(高校生年代まで)の日本国内に住んでいる児童を養育している、江戸川区内に住民票のある保護者(父または母等)で、ご家庭での生計中心者(注)となっている方が、支給対象者(請求者)となります。手当を受給するためには申請が必要です。
(注)生計中心者とは、児童の父または母で所得が高い方です。
父母ともに所得がある場合には、原則として恒常的に所得の高い方になります。
1-1.生計中心者が児童と別居している場合
児童と別居していても申請できます(申請先は、生計中心者の住民票がある自治体になります)。
1-2.生計中心者が外国人の方の場合
生計中心者の住民票が江戸川区内にあれば、対象となります。
1-3.生計中心者が公務員の方の場合(公務員共済組合に加入した場合を含む。)
勤務先で児童手当を支給しますので、勤務先に申請してください。
配偶者の方が公務員で、勤務先へ申請済みの場合、江戸川区への申請はできません。
詳しくは、「よくある質問(10)公務員になりました。または、公務員を退職しました。必要な手続きは?」をご覧ください。
1-4.児童の住民票が国内にない場合
児童が海外で生活している場合は申請できません。なお、留学中の場合はご相談ください。
2.支給額・支給月・支給方法
2-1.支給額(1人あたりの月額)
| 児童の年齢 | 支給額 | |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
|
3歳未満 |
15,000円 | 30,000円 |
| 3歳から高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
(注)第何子目かを数える際には、高校生年代までの児童と、児童手当の受給者が経済的な負担等をしている18歳年度末経過後から22歳年度末までの子(児童の兄姉等)の合計人数を数えます。
2-2.支給月
| 支給月 | 支給対象月 |
|---|---|
| 10月 | 8月分・9月分 |
| 12月 | 10月分・11月分 |
| 2月 | 12月分・1月分 |
| 4月 | 2月分・3月分 |
| 6月 | 4月分・5月分 |
| 8月 | 6月分・7月分 |
2-3.支給方法
請求者名義の口座に振込します。児童や配偶者の方の口座には振込できません。
また、対象児童が2名以上の場合でも、振込口座は1つです。
公的給付支給等口座(公金受取口座)への支給もできます。公金受取口座登録制度については、デジタル庁ホームページ![]() をご覧ください。
をご覧ください。
振込先の変更を希望する場合は、6.こんな時にはお手続きが必要ですをご覧ください。
3.申請方法
申請は生計中心者(児童の父または母で所得が高い方)が行います。「窓口」・「郵送」・「電子」のいずれかの方法により申請してください。
| 窓口 |
本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口でのみ受付します(各事務所では受付していません)。 |
|---|---|
| 郵送 |
児童家庭課に書類が到着した日が、申請日となります。 |
| 電子 |
ぴったりサービスを利用した電子申請での手続きも可能です。(ログイン・電子署名必須)
(注)別途、郵送での手続きが必要な場合があります。 |
3-1.申請にあたっての注意事項
- 手当の支給開始月について
申請日の翌月が手当の支給開始月となります。申請が遅れた場合、さかのぼって支給はできませんので、お早目にご申請ください。 - 月の後半に出生または転入した場合について
月の後半に出生または転入した場合、その日の翌日から数えて15日以内(出生は出生日の翌日から15日以内、転入は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)に申請した場合には、出生等の月に申請があったものとみなされます(15日特例)。- (例1)4月30日出生(または転出予定日)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされます。
したがって5月分から手当が開始となります。 - (例2)4月30日出生(または転出予定日)で5月16日に申請した場合、5月中の申請となります。
したがって6月分から手当が開始となります。
- (例1)4月30日出生(または転出予定日)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされます。
3-2.申請者の代理人が窓口で申請する場合(配偶者の場合など)
以下のものをご用意いただき、窓口で申請してください。
- 委任された方の身元確認ができるもの(免許証、パスポート等)
- 請求者のマイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し、いずれか1点)
- 委任状(下記より様式をダウンロードできます。)
4.必要書類
4-1.児童手当認定(額改定)請求書
本庁舎及び各事務所の窓口でお渡ししています。
「認定(額改定)請求書」は下記からも様式をダウンロードできます。
- 児童手当認定(額改定)請求書(PDF:560KB)

- 児童手当認定(額改定)請求書(記載例)(PDF:800KB)

- 【英語版 English ver.】児童手当認定(額改定)請求書【記載例】(PDF:720KB)

ぴったりサービスを利用した電子申請での手続きも可能です。(ログイン・電子署名必須)
児童手当を新たに申請する場合は、マイナポータルの「児童手当の申請」![]() から申請してください。
から申請してください。
(注)電子申請の場合、別途、郵送での手続きが必要な場合があります。
4-2.身元確認書類
申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については以下の「マイナンバー(個人番号)申請時の本人確認について」をご覧ください。
区分Aまたは区分Bいずれかの身元確認書類が必要です。
(注)「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があるものが必要です。
区分A(1種類お持ち下さい)
- 顔写真付身分証明書
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、社員証・職員証、学生証、資格証明書
区分B(2種類お持ち下さい)
- 顔写真無し身分証明書
例:資格確認書(健康保険証)、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証・職員証、学生証、資格証明書 - 公的書類
例:印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、ひとり親家庭等医療費助成医療証、心身障害者医療費助成受給者証、公害医療手帳、被爆者健康手帳、自立支援医療受給者証、特定医療費受給者証、大気汚染医療費助成医療券、特定疾病療養受療証、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療券 - 自治体発行の通知文書等
例:地方税・国税の納税通知書、社会保険料納付通知書 - 地方税等の領収証等
例:地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収証、納税証明書等 - その他
例:江戸川区や東京都が発行した予め氏名等が印字された届出等
4-3.マイナンバー(個人番号)確認書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーの記載のある住民票の写し
いずれか1つご用意ください。
身元確認書類とマイナンバー確認書類のご提出がないと、マイナンバーを利用した情報照会が出来ないため、別途、課税証明書・住民票の写し等の提出が必要になる場合があります。
郵送申請の場合はコピーを同封してください。
4-4.申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
郵送申請の場合は、コピーを同封してください。
ネット銀行で通帳やキャッシュカードがない場合は、各銀行のマイページ等で銀行名・支店名・口座番号・口座名義が確認できる部分の画像等を印刷し、同封してください。
以下の書類は場合により必要です
4-5.養育事実の同意書 単身赴任などで児童と別居している方
児童の属する世帯の世帯主の方の同意が必要になります。
児童が区外にお住まいの場合は、児童のマイナンバー(個人番号)を記載してください。
「養育事実の同意書」は以下から様式をダウンロードできます。
4-6.戸籍の附票の写し 日本国籍の方
日本国籍の方で、課税基準日(下記【別表1】参照)に海外に居住していた方は、戸籍の附票の写しが必要です。
(注)海外へ転出した年月日、日本へ帰国し住所を定めた年月日が確認できるもので、江戸川区への転入まで記載のあるものをご用意ください。
(注)本籍地にご請求ください。
(注)ひとり親世帯の方は、提出は不要です。
4-7.パスポート 外国籍の方
外国籍の方で、課税基準日(下記【別表1】参照)に日本国内に住民登録していなかった方(入国日が課税基準日以降の方)は、「パスポートのコピー(顔写真、名前及び課税基準日に日本にいないことがわかる部分)」を提出してください。
(注)ひとり親世帯の方は、提出は不要です。
| 手当の対象月 | 所得判定年度 | 課税基準日 |
|---|---|---|
| 令和6年6月から令和7年5月 | 令和6(2024)年度(令和5年1月から12月までの所得) | 令和6年1月1日 |
| 令和7年6月から令和8年5月 | 令和7(2025)年度(令和6年1月から12月までの所得) | 令和7年1月1日 |
4-8.児童の兄姉等(18歳年度末経過後から22歳年度末までの子)がいる方
児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(注)児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に提出が必要です。
4-9.その他
上記以外で必要な書類がある場合は、個別にご連絡します。
5.申請にあたっての注意事項
- 児童手当は申請日の翌月から支給されます。
申請が遅れた場合、さかのぼって支給はできませんので、お早目にご申請ください。 - 必要書類がそろわない場合は、認定(額改定)請求書のみご提出いただければ、提出日(郵送の場合は到着日)を申請日として受付します。不足書類はそろい次第、ご提出ください。ただし、申請後、一定期間(およそ3か月)を経過しても不足書類のご提出がない場合、申請は却下されますのでご注意ください。
- 同じ月内で江戸川区へ再転入した場合も、その都度、児童手当の申請が必要です。
- 児童手当の受給資格の認定後、支給開始月・額等を記載した「児童手当認定通知書」を送付します。送付は、申請いただいてから1か月から2か月後(5月・6月に申請した方は2か月から3か月後)です。
6.こんな時にはお手続きが必要です
6-1.江戸川区外へ転出する場合
児童手当の受給者の方が区外に転出すると、江戸川区からの児童手当は消滅になります。
転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転出先の区市町村で新たに児童手当を申請してください。
申請が遅れると、手当を受け取れない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。
必要書類など詳しくは転出先の自治体にお問い合わせください。
6-2.振込口座の変更をする場合
受給者名義の口座にのみ変更可能です。児童や配偶者の方の口座には変更できません。
以下より様式をダウンロードできます。
児童手当の支給月が近づいてからの変更になりますと、ご希望の月からの変更ができない場合もありますので、予めご承知おきください。
なお、郵送にて変更される場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーを同封してください。
ネット銀行で通帳やキャッシュカードがない場合は、各銀行のマイページ等で銀行名・支店名・口座番号・口座名義が確認できる部分の画像等を印刷し、同封してください。
6-3.第2子以降の児童が生まれた場合
認定(額改定)請求書の提出が必要です。ご出生された翌日から数えて15日以内にご申請ください。
現在受給中の児童も含めてご記入ください。
第2子以降の追加申請をする場合、普通預金通帳またはキャッシュカードのコピー、資格確認書(健康保険証)のコピー、マイナンバー(個人番号)等の提出は不要です。
下記より様式をダウンロードできます。
ぴったりサービスを利用した電子申請での手続きも可能です。(ログイン・電子署名必須)
既に児童手当を受給しており、増額の申請をする場合は、マイナポータルの「児童手当で児童の人数に変更があったとき」![]() から申請してください。
から申請してください。
(注)電子申請の場合、別途、郵送での手続きが必要な場合があります。
6-4.その他、手続が必要となる場合
以下の事由が発生した場合は、届け出が必要です。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や国外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童がいる方で、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合、届け出は不要です。)
- 受給者が公務員になったとき(会計年度任用職員が共済組合に加入した場合を含む)
- 離婚協議中の受給者の離婚が成立したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記載した児童の兄姉等(18歳年度末経過後から22歳年度末までの子)の状況が変わったとき
7.児童手当の更新手続(現況届)について
次に該当する方は、養育状況等を確認し、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかの審査を行うため、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
- 江戸川区外に支給対象児童(0歳から18歳年度末までの子)の住民票がある方
- 江戸川区外に算定対象者(多子加算の対象者で18歳年度末以降~22歳年度末までの子)の住民票がある方
- 算定対象者(多子加算の対象者で18歳年度末以降~22歳年度末までの子)の職業等を「無職」または「その他」で登録している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地と実際の居住地が異なる方
- 児童等の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人の方
- 施設等の受給者の方
- その他提出の案内があった方
詳しくは、「児童手当「現況届」について(2025年(令和7年)度)」をご覧ください。
8.児童手当についてのよくある質問
児童手当について、みなさんからお問い合わせいただく主なものをまとめました。以下の「児童手当のよくある質問」をご参照ください。
9.児童手当のご案内
「児童手当のご案内」(PDF:44KB)![]() をご覧ください。
をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 児童手当・子ども医療費助成・ひとり親への支援 > 児童手当