更新日:2025年4月9日
ページID:23521
ここから本文です。
睡眠と健康
目次
睡眠とは
睡眠はなぜ必要か
睡眠は健康の維持・増進に不可欠な休養活動です。良い睡眠は、身体的な健康だけでなく、精神的な健康の維持・増進にも欠かせません。また、労働災害や交通事故などの眠気や疲労が原因となる事故のリスク低減にもつながります。
では、良い睡眠とはどのような睡眠のことをいうのでしょうか。

睡眠時間と睡眠休養感
「朝になかなか起きられない」「日中に眠気が襲う」「休日に寝だめをしてしまう」といったことはありませんか?
それは良い睡眠がとれていないサインかもしれません。
良い睡眠は、睡眠時間(量)と睡眠休養感(質)が十分に確保されることで得られます。その両方を確保するためのヒントを「世代ごとの睡眠」と「より良い睡眠づくり」で紹介していきます。
睡眠時間
睡眠の量を反映する指標といえます。
量をとればいいというわけではありません。寝ることができる時間には限りがあり、必要な睡眠時間は年齢や季節によっても変化します。また、休日にまとまって多く眠る「寝だめ」も有効ではありません。平日の睡眠が6時間未満の場合は、休日に寝だめをしても寿命短縮リスクが高まることが報告されています。
睡眠休養感
睡眠の質を反映する指標といえます。
朝目が覚めたときの睡眠休養感は、良い睡眠がとれているかどうかの指標にもなります。睡眠時間の不足だけでなく、睡眠環境や生活習慣などのさまざまな要因から影響を受けます。一方で、それらを改善しても睡眠休養感が十分に得られない場合は、睡眠障害が潜んでいる可能性があります。
世代ごとの睡眠
子どもの睡眠

- 小学生は9時間~12時間、中学・高校生は8時間~10時間を参考に睡眠時間を確保する。
- 朝は太陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、夜ふかしの習慣化を避ける。
大人の睡眠
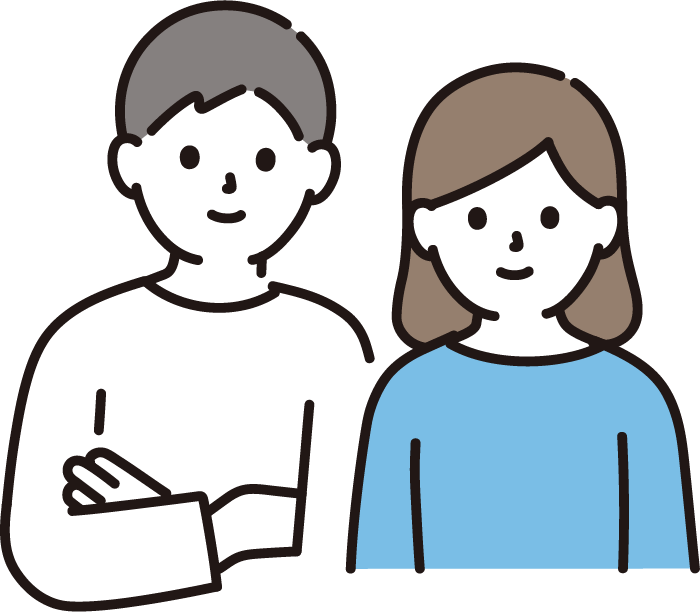
- 適正な睡眠時間には個人差があるが、6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保する。
- 食生活や運動等の生活習慣、寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。
- 睡眠の不調・睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣等の改善を図ることが重要であるが、病気が潜んでいる可能性にも留意する。
熟年者の睡眠
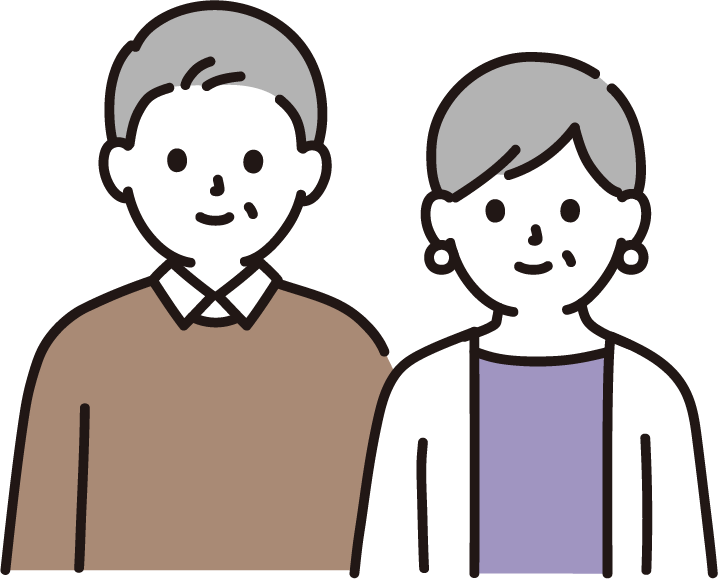
- 長い床上時間が健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安に、必要な睡眠時間を確保する。
- 食生活や運動等の生活習慣、寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。
- 長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中は長時間の昼寝は避け、活動的に過ごす。
より良い睡眠づくり
ライフスタイルが多様化する中、睡眠に対する感覚や睡眠を確保する手段は、個人によってさまざまです。より良い睡眠を得るためのヒントを「睡眠環境」「生活習慣」「嗜好品」に分けて紹介しています。どれかひとつでもみなさんの素敵な睡眠ライフのために取り入れてはいかがでしょうか。
睡眠環境
光
- 起床後に朝日を取り入れ、日中にできるだけ日光を浴びる。
- 寝る前にはスマートフォンや照明などの強い光を避ける。
- 就寝時はできるだけ暗くして眠る。

起床後に朝日を浴びることで体内時計がリセットされ脳の覚醒度が上がり、気持ちのいい目覚めにつながります。日中にできるだけ日光を浴びることで、夜間に睡眠を促すホルモンであるメラトニンの量が増加し、眠りにつきやすくなります。また、就寝の2時間前からメラトニンの分泌が始まります。そのため、それ以降に照明やスマートフォンの強い光を浴びると、メラトニンの分泌が抑制され、睡眠・覚醒のリズムが崩れることで寝つきが悪くなるといわれています。
起床後はすぐにカーテンを開ける、夜間は照明を減らす、寝室にスマホを持ち込まないなどそれぞれの生活にあった工夫を取り入れてみてはいかがでしょうか。
温度
- 就寝の約1~2時間前に入浴する。
- 寝室は暑すぎず寒すぎない温度に保つ。
- 季節に合った工夫をする。
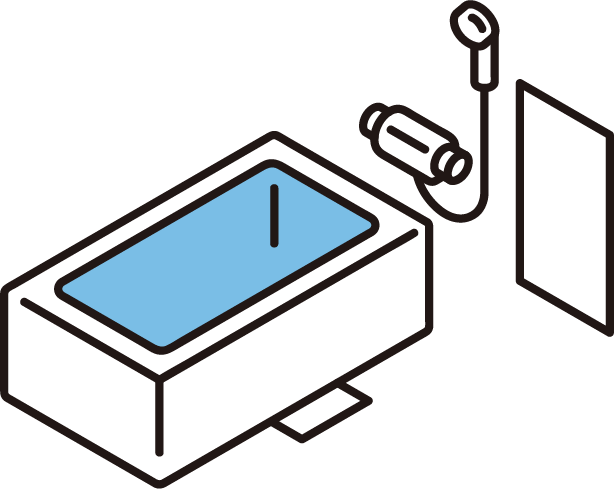
深部体温(身体内部の温度)は、日中の起きている間に上がり、夜間の睡眠時に下がります。就寝の約1~2時間前に入浴することで深部体温の低下をスムーズにし、ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間を短くする効果があるといわれています。また、夏は寝室の室温が上がることで睡眠時間が短くなり、睡眠効率が下がることが報告されています。そのため、夏はエアコンを用いて涼しい状態を保つことが重要です。冬は睡眠後に室温の影響を受けにくいといわれていますが、寝具を用いて暖かくすることが重要です。
スムーズに眠りにつくため、入浴を習慣化し、季節に合わせて室温や寝具を整えることを意識してはいかがでしょうか。
生活習慣
運動習慣
- 適度な運動習慣を身につける。

運動習慣がない人は、睡眠休養感が低いことが分かっています。日中に身体をしっかり動かすことで、寝つきをよくし、中途覚醒(睡眠途中に目が覚めてしまうこと)を減らすことが期待できます。一方で、就寝前1時間以内の激しい運動は、夜の眠りを妨げる可能性があります。夕方や夜に運動する場合は、就寝の約2~4時間前までにしましょう。
睡眠だけでなく、健康増進のためにも1日60分程度の身体活動を習慣化させることが理想ですが、まずは1日60分未満でも定期的な運動習慣を身につけ、少しずつ運動時間を増やしていきましょう。また、運動の頻度は週2回以上行う方がより効果的です。おすすめは、息が弾み汗をかく程度の有酸素運動(ウォーキングなど)や筋力トレーニングです。日常に運動を取り入れるヒントについては「運動」のページをご覧ください。
食生活
- 朝食をしっかりとる。
- 就寝直前の夜食を控える。

朝食を食べることは、体内時計を整えることに役立ちます。一方で、就寝前の夜食や間食は、体内時計を狂わせる要因になるといわれています。また、塩分をとりすぎると夜間の排尿回数が増えるため、減塩を心がけることで、睡眠中に尿意により目覚める回数を減らすことが期待できます。
日常生活のリズムを整えるために、朝食を含む3食をなるべく決まった時間にとり、バランスのよい食事を心がけましょう。朝食を食べるためのコツや減塩については「栄養」「減塩を心がけましょう」のページで紹介しています。
嗜好品
カフェイン
- 摂取量は1日400mg(コーヒー700ml程度)を超さない。
- カフェインを夕方以降に摂らない。

カフェインは覚醒作用があるため、寝つきの悪さや中途覚醒の増加、眠りの質の低下を起こす可能性があります。またカフェインの代謝には個人差があり、血液中のカフェイン濃度が半分になるのに3~7時間とばらつきがあります。なお、子どもはカフェインの影響を受けやすく、熟年者は代謝が低下しているため、カフェイン量を減らすことが大切です。
カフェイン摂取量を減らし控えていくためには、カフェインの含まないものに置き換える(ハーブティー、麦茶、そば茶、黒豆茶、とうもろこし茶など)ことがおすすめです。
また、カフェインはコーヒーやお茶だけでなく、エナジードリンクや栄養ドリンクにも含まれています。飲み物を選ぶ際には注意してみましょう。
お酒
- 晩酌は控えめにし、深酒はしない。
- 寝酒(寝るためのお酒)はしない。

お酒は一時的に寝つきを促進しますが、睡眠後半の眠りの質は悪化し、中途覚醒の回数が増加するといわれています。また繰り返しお酒を使うことで依存や耐性がつき、お酒がないと眠れない状態になってしまう可能性があります。
睡眠のために、毎日の飲酒は避け、晩酌は控えめにし、お酒以外の睡眠習慣を探してみてはいかがでしょうか。お酒との上手な付き合い方については「お酒」のページをご覧ください。
また、お酒がないと寝られないなど体調や生活がお酒に影響される方は、医師に相談することが推奨されます。各健康サポートセンターでもご相談をお待ちしています。
ニコチン
- 喫煙(紙巻たばこ、加熱式たばこ等のニコチンを含むもの)は避ける。

ニコチンは覚醒作用があるため、習慣的なニコチンの摂取が、寝つきの悪さや中途覚醒の増加の原因になります。また、睡眠時間の減少や日中の眠気が強くなるとも言われています。受動喫煙も同じように睡眠に影響を及ぼすため、喫煙する場合は周りへの配慮が必要です。
喫煙が悪化させるのは睡眠だけではありません。禁煙を目指しましょう。たばこについては「たばこと健康」のページで詳しく紹介しています。
これまでに紹介したもの以外に、音楽を聴く、アロマオイルを焚くなど自分なりのリラックス方法を見つけることも、より良い睡眠に不可欠です。ぜひ自分らしい睡眠を楽しみながら探してみてください。
より良い睡眠づくりについて、もっと詳しく知りたい方は参考資料をご覧ください。
その他
睡眠障害

睡眠に関する症状は、「睡眠環境、生活習慣、嗜好品」によるものと「睡眠障害」によるものがあります。前者に起因する睡眠関連症状は、日常生活を整えることで改善が期待できます。しかし、日常生活を変えても睡眠に関連する症状が続く場合、睡眠障害が潜んでいる可能性が考えられます。そのような場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
妊娠・子育て・更年期の睡眠

睡眠はホルモンバランスに影響されます。そのため、月経周期や妊娠、更年期によって睡眠の悩みが増えることが多いです。
妊娠中の睡眠は妊娠経過とともに変化し、胎児の健康にも影響する可能性があり、子育て期の睡眠も健康増進・維持には重要です。また、更年期には睡眠の悩みが再び増える傾向にあります。
妊娠期や更年期の悩みは、日常生活を整えるだけでは改善しない可能性もあります。必要に応じて医療機関に相談しましょう。また、親子の健康習慣については「まいにち成長、おやこで健康」をご覧ください。
就業形態と睡眠課題

交替制勤務では、睡眠の不調などの健康リスクに注意が必要です。不眠や睡眠休養感の低下、業務中に眠気が続き、日常生活に支障を来している場合は速やかに医療機関を受診することをお勧めします。
各種相談
参考資料
- 厚生労働省-健康づくりのための睡眠ガイド2023

- 厚生労働省-健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023

- 厚生労働省e-ヘルスネット「健やかな睡眠と休養」

- 厚生労働省e-ヘルスネット「睡眠と健康」

本ページは「健康づくりのための睡眠ガイド2023(厚生労働省)」をもとに作成しています。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > みんなの健康応援サイト > 健康づくり(歯・栄養・運動など) > 大人の健康 > 生活習慣改善のための健康生活へのヒント > 睡眠と健康




