ここから本文です。










更新日:2024年7月12日
11月の行動:最新の科学や技術に興味を持ち、活用してみよう
ICTの活用で広がる、子どもたちの新たな学び

GIGAスクール構想(注1)に基づいて区内小・中学校の子どもたちに配布されている学習用タブレット端末。このタブレットを使ったICT(注2)教育が各学校で進められています。子どもたちはどのようにICTを活用しているのか、授業の様子をのぞいてみましょう。
(注1)児童・生徒1人1台のコンピューターと高速ネットワークを整備することで、子どもたちの創造性を育む教育の実施やICT環境の実現などを目指す、文部科学
省が令和元年に開始した取り組みのこと。
(注2)Information and Communication Technologyの略で、パソコンやタブレットなどを活用した情報処理や通信技術のこと。
「たくさん調べられたよ!」
鹿骨東小学校2年生の生活科の授業。この日はヤゴの生態について調べ学習を行います。
先生が「じゃあタブレットで調べてみよう」と声をかけると、子どもたちはタブレットを使って検索を始めました。さまざまな単語を検索窓に入力し、思い思いに調べる子どもたち。しばらくすると「先生、こんなページを見つけたよ!」「“ヤゴからトンボの成長の仕方”って調べたら結構出てきたよ」「分からない…」と子どもたちからさまざまな声が。先生は「たくさん調べられたね」「ここを押してみたらいいんじゃないかな」など一人ひとりに声をかけます。また、先生のタブレット画面をモニターに映し出し、参考となるページを共有しながら子どもたちの学習のサポートを行います。
こうして子どもたちはたくさんの情報を集め、分かったことを手元のプリントにまとめることができました。
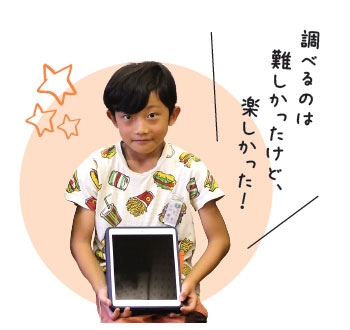
ICT活用によるさまざまなメリット

それぞれ自分のペースで調べ学習を進めています
「タブレットを使うことで、従来よりも効率的に調べ学習ができるようになりました」と話すのは同校の中田伸代校長。1人1台持っているタブレットを使用すれば全員が「同時に」「個別に」調べ学習を進めることができる他、まだ読めない漢字が多い低学年のクラスでは漢字にふりがなをつける機能を活用し、自分で文章を読み進めることができるのだそうです。
さらに、休み時間にタブレットから音楽を流して自主練習を行うダンスクラブや、委員会活動で使用する動画を撮影する子、インターネットで気になる活動を見つけたからやってみたいと相談にやってくる子など、子どもたちの自発的な行動も増えたといいます。先生が準備したものではなく、子ども自身が見つけ・考えたことを行動に移せるようになったこともICT活用の大きなメリットになっています。
広がる学びの可能性
一方で、「これまでのような、人と関わる学びも大切」と中田校長は話します。「従来の学び方とICTの活用をうまく融合させることで、子どもたちのさまざまな能力を伸ばし、社会に出た時に役立つ力を育んでいきたいですね」
これまでの学校教育に加え、ICTの活用に積極的に取り組んでいる学校現場。子どもたちの学びの可能性は確実に広がっています。
他にもこんな授業を行っています!
小学6年生のハードル走の授業では、走っている姿をタブレットで撮影し、フォームの確認を行っていました。
子どもたちは自分の姿を客観的に見たり、友達からアドバイスをもらったりして、技術の向上に努めていました。
Act!さあ行動しよう
第24回 産業ときめきフェア in EDOGAWA
製造業を中心とした企業・団体が一堂に会し、展示・実演などを通して優れた製品・技術力を紹介します。
日時
11月18日(金曜日)午前10時~午後5時・19日(土曜日)午前10時~午後4時
場所
タワーホール船堀1階展示ホール ほか
内容
- 展示→区内外に誇れる製品・技術の紹介、区制90周年企画展示 ほか
- ビジネスセミナー(18日(金曜日))⇒中小企業の社内DX推進セミナー ほか
- 日本化学会オンライン講演会(19日(土曜日))⇒「今まさに結晶ができるところを見る」 ほか
- ものづくり体験(19日(土曜日))⇒ロボットプログラミング体験 ほか
問い合せ
ものづくり産業係 電話:03-5662-0525
区民ニュース![]() で関連動画を放映中!
で関連動画を放映中!
お問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 計画・目標 > 区政運営 > さあ!やってみようSDGs > さあ、やってみよう!SDGsえどがわ10の行動 > 特集シリーズ SDGsえどがわ10の行動 > 11月の行動:最新の科学や技術に興味を持ち、活用してみよう