更新日:2025年5月1日
ページID:20454
ここから本文です。
葛西沖 vol.4 なぎさの形に秘めた思い
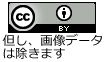
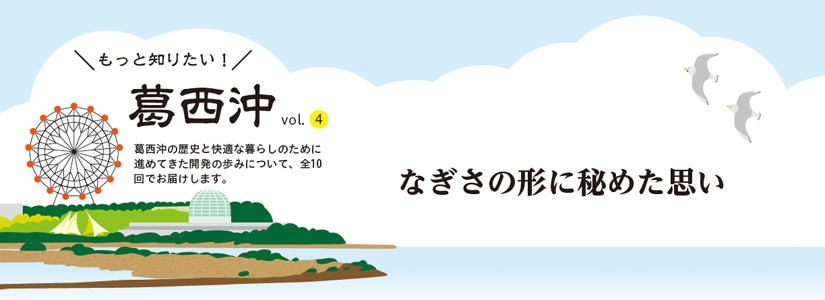
利用目的の異なる2つの人工なぎさ
葛西海浜公園にある2つの人工なぎさは、それぞれ特別な役割を担っています。
「西なぎさ」は、水遊びをしたり、カニやハゼなど干潟の生き物を観察したり、レクリエーションを楽しめる場として造られました。
もう一つの「東なぎさ」は、陸域側からのさまざまな影響から天然の干潟を保護する役目を担っています。野鳥が飛来し、羽を休める様子も見られる東なぎさは、海で暮らす魚類や貝類、鳥や植物などの生物を守るため、人の立ち入りが禁止されています。
三枚洲(さんまいす)干潟を守る人工なぎさ
海浜公園を計画していた当時、人工なぎさ(海浜)を造った事例は、沖縄国際海洋博覧会会場のエメラルドビーチ(昭和50(1975)年完成)など、世界にいくつかありました。しかし、それらはレクリエーションの利用を主目的としており、葛西海浜公園のように三枚洲干潟の保全と生物の生息環境保護、レクリエーションの機能を併せ持つ人工なぎさを造った例は過去にはありませんでした。そのためこれらの機能が調和した人工なぎさを目指し、模索が続けられました。
「生物相を多様化するために広い潮間帯をつくる」「三枚洲を変形しない」「シギ・チドリ類の餌が捕れるような潮入りの干潟にする」「風土条件に適した地形となるような平面や断面計画とする」「生物の保護とレクリエーションとが共存できる」といった複数のテーマを条件に挙げて検討を重ねた結果、総延長2キロの人工なぎさを2つに分離し、東を生物保護区、西をレクリエーション区とすることになりました。
また、現在のようになぎさを2つに分割することで生まれる水路は、公園内の水質浄化に役立つことも分かってきました。

人工的に造られた西なぎさ(左)と東なぎさ(右)
年単位の研究調査が続く
検討の過程で特に注目したのは、人工なぎさで生物相がどのように回復してくるかについてでした。生物の数の増減のみならず、天然の干潟で生息している種とも比較して回復状況を確認しました。
海浜公園の計画から完成まで20年という長い年月はかかりましたが、計画の段階から地道な研究・調査を続けてきたからこそ、自然を回復しながら多くの人が楽しめる場が生まれ、私たちはよみがえった海の姿を見ることができました。
現在では、東なぎさを中心にハゼ、カニ、貝そして鳥たちの楽園になっています。
ご意見・ご感想は都市計画課調整係へ 電話:03-5662-6368
トップページ > シティインフォメーション > 広報・広聴 > 広報えどがわ > 連載 > 連載 もっと知りたい!葛西沖 > 葛西沖 vol.4 なぎさの形に秘めた思い




