ホーム > 未来へのヒント > インタビュー・広報記事 > 対立は「恐怖」から 必要なのは飛び込むこと
ここから本文です。
インタビュー・広報記事
Interview・Public relations
対立は「恐怖」から 必要なのは飛び込むこと
17歳で小説家デビューを果たし、以来、社会の仕組みや人間の心理を緻密に描き出す鋭い切り口で物語を紡ぎ続けてきた羽田氏。作家としての歩みはもちろん、大学時代の一人暮らし、さらには「この世界や社会は見方によって変わってくる」という考え方まで、情報過多な現代社会で何に注目し、どのように生きるべきか——羽田氏に自身の経験を交えながら語っていただきました。
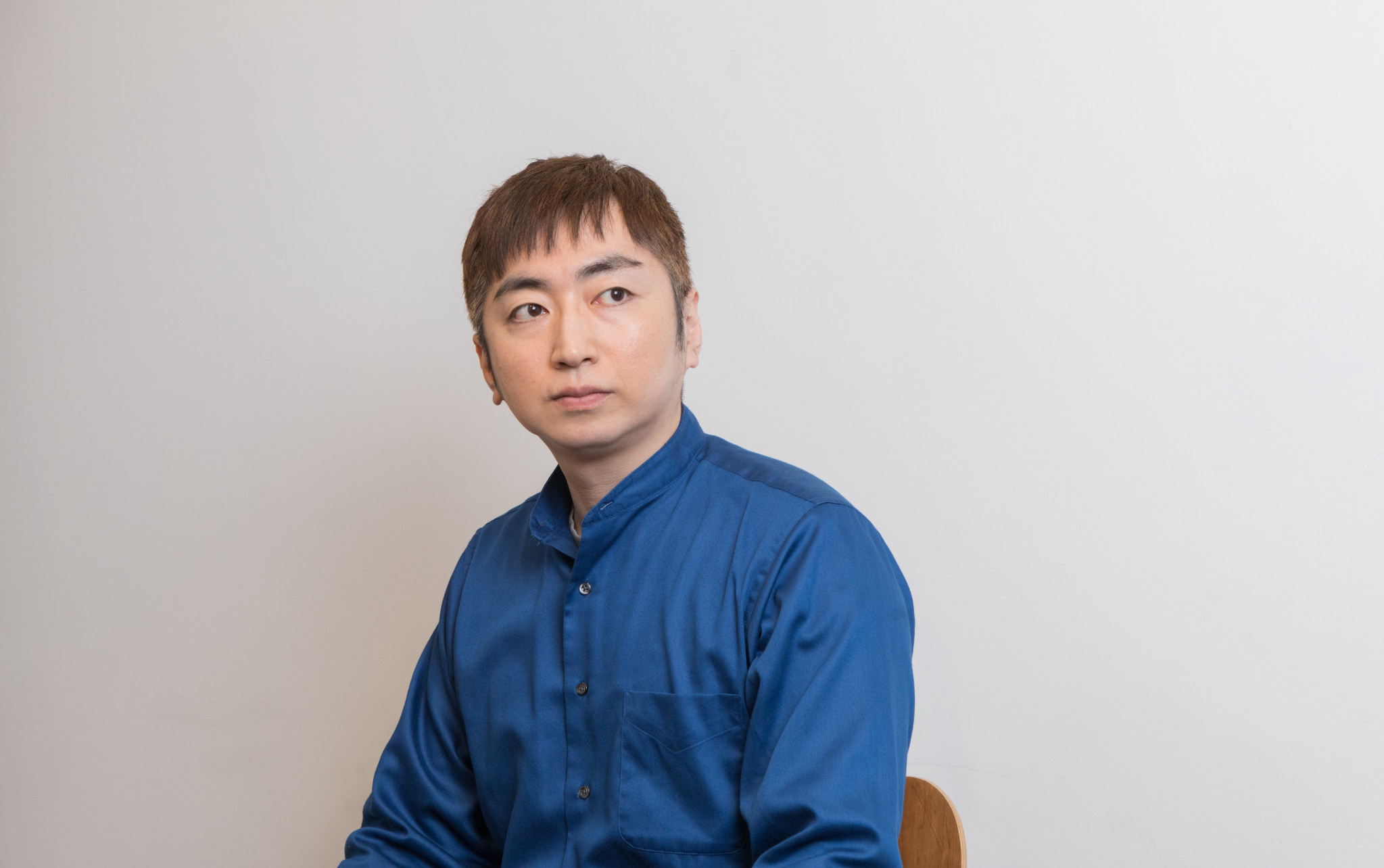
17歳で小説家デビュー 江戸川区で始めた一人暮らし
羽田さんのご経歴を教えてください。
小説家としてデビューしたのは17歳、高校生の時。『黒冷水』(2003年 河出書房新社)で第40回文藝賞を受賞しました。その後、明治大学に進学。附属中学時代より、埼玉の実家から通学していましたが、大学3年生の終わり頃に「実家だとインテリアを好きにできない」と思い、江戸川区に引っ越しました。家賃9万1000円の賃貸マンション。就活が始まる忙しい時期に、初めての一人暮らしをスタートさせました。「御茶ノ水までの通学の時間も短縮でき、たくさん執筆できる」と意気揚々でしたが、大学4年になると出席する講義も少なくなっており、特に筆が進むわけでもなかったので、かかるのはお金ばかり。後期が始まる頃には埼玉の実家に戻りました。卒業後は企業に1年半ほど就職し、2009年から専業小説家になりました。
江戸川区での一人暮らしはどうでしたか?
住んでいたのは8か月くらいでしょうか。たまに江戸川へ自転車で行って、千葉のあたりまで走ったりもしていました。埼玉の実家も、限りなく千葉や東京に近いところにあったので、中学〜高校時代、電車以外だと自転車しか交通手段がなかった僕にとっては、川沿いのサイクリングロードは東京までの“高速道路”代わりでした。地元の松伏から江戸川に出て、サイクリングロードと国道6号線伝いに浅草まで行って帰ってくるなどよくしていましたね。河川敷の、自然の多い空が抜けた風景が印象的です。

本を手に取ってもらう機会が減る恐怖
小説家の道に進まれたきっかけは何でしたか。
埼玉の実家から、御茶ノ水にあった中学・高校まで電車で通学していました。毎日往復2時間ほどの通学電車内で暇をつぶす方法といえば、MDで音楽を聴くか、本を読むかでした。3日に1冊のペースで読んでいました。そのうちに、「これだけ読んでいれば僕も書けるのでは」と、小説家に憧れをもつようになります。そうして、初めて投稿したのが『黒冷水』です。『黒冷水』の前に、『走ル』(2008年 河出書房新社)の原型となるひたすら自転車で走りまくる作品や、校内暴力…行き過ぎた正義の暴力をテーマにした作品を書いていましたが、どちらも自分でボツにしました。『黒冷水』という小説はよくまとまっていますが、むしろ、ボツにした自転車で走りまくる作品の方が、破綻するギリギリの境界にまで挑んでいましたね。結果、そのときは満足のいく形としてはまとめきれなかったわけですが。
初めから小説家一本というわけではなかったのですね。
中学から私立に10年間通わせてもらっていて、新卒採用の権利を行使しないのは、学費を払ってくれた親に対してどうなのだろうという思いがありました。就職する方が僕自身楽だったのです。小説家という仕事も続けていれば色々な仕事を含むものなので、人生経験としては、長い目でみればどちらでもよかったかなと思います。
デビュー作がかなり読まれたわりに、2、3作品目はデビュー作ほどとまではいきませんでした。専業小説家になってしばらく経つうちに、新刊を出しても書店に少ししか並べてもらえないことも増えていきました。都心の大型書店ですら、平積みではなく本棚に背表紙が見えるだけの形で棚1冊だけという経験もあります。純文学とエンタメで分けられていた棚がまとめられ、やがて棚の数自体が減っていき、ハードカバーの棚が文庫本の棚と入れ替わり、店内の奥の方になっていきました。文芸作品のハードカバーが人の目につくことは、どんどん減っていくのではないかという不安がありましたね。既存の読者の方にインターネット上で買っていただけることはあっても、書店でふらっと手に取って買っていただくといった、新規の読者が増えることはこの先減るかもしれないという危機感を感じていました。しかし、これは単に自分が執筆を頑張ったり、書店を応援したりするだけでは変えられないと感じています。「書店は減ってほしくない」「文芸作品をたくさん並べてほしい」という想いはもちろん強いです。そのうえで、確実に現状をどうにかしたいのであれば、無駄なくまともな経済政策を打つ政治家に投票し、経済からなる構造自体を変えていくこともかなり大事です。一人一人の可処分所得が増えれば、本にお金をかける余裕が生まれるかもしれません。一見遠回りに見えることこそが、確実に変えていける一手だと思っています。

「幸せ」はものの見方で変わる
最近はどのような作品を書かれていますか?
最近出版した、『バックミラー』(2025年 河出書房新社)という短編集では、ここ十数年間で書き溜めた短編小説を抜粋し収録しているのですが、その時自分がどういう状況で書いていたかが如実に表れています。同じ東京という土地で書いてきたはずなのに、電車移動だけだった頃とタクシー移動もするようになった頃の東京とでは見え方が違います。自分で車を買って、自由に地方などにも行ける状況で見る東京ともなると、さらに自分の中に違う捉え方がでてきます。東京に十数年間住んでいても、少し視点が変わることで見える世界が違ってくるのは、とても興味深いことだと感じています。要は、この世界や社会は見方によって変わってくると思うのです。だからこそ、様々な視点を持つことが重要です。
若い頃の方が幸せだったという人も多いですが、それは無限に可能性を感じていた夢を見る無邪気さによって支えられた「幸せ」な部分が大きいと思います。僕は今39歳ですが、昔よりは無邪気な夢想はしなくなりました。大切なことの取捨選択や、それは無謀すぎるからやらなくていい等の判断ができることで、大事なことに注力できたり、その時点からまた別の楽しいことを見つけたりもできます。
様々な視点を理解する上ではどのようなことが必要でしょうか。
その人の生まれや属性に左右されないという点において、本を読むのが一番いいです。それ以外ですと、いろんな人と話したり接したりする場に身を投じるしかないですよね。たとえば、同じ学校に通っていたとか、昔からの知り合いたちは、その当時までは育ってきた環境や価値観が似たもの同士である場合が多かったと思います。そこから社会に出ていくうちに、色々なことの“差”は徐々に開いていきます。しかし、そこの差を意識せずに過ごしている人も少なくないのではないでしょうか。僕も最近、久々に会った古くからの友人との間に、価値観の違いを感じたことがありました。端折って話すと、その人にはかなりの稼ぎがあるにもかかわらず、家賃をケチるために職場からものすごく遠いところに賃貸で住み、電車通勤に毎日5時間以上もかけ、家にいる子供たちと全然接せられていないということです。薄給の人が貯蓄のためにそれをするのならまだ理解できるのですが…。
いっぽうで、最近会った台湾の方は、色々なことに関して僕の価値観と近く、一緒にいてすごく楽でした。特にお金持ちというわけでもないのですが、お金は使うべきところには使うという考えの人でした。
つまり、学生の頃は近しい価値観だった同じ言語の人とはいつの間にか考え方がズレてきていたなんてこともあったり、異文化・異言語であれど、蓋を開けてみれば同じ価値観の人もいたりするというわけです。接してみないと通じ合えるかは分からないのです。接してみて、どこに“価値観の差”があるか気づくことで、衝突する前に接し方を変える事ができるのではないでしょうか。
対立を生まないために必要なこと
羽田さんは生活する上でどういったことに注視していますか?
僕の家にはテレビがありませんし、ネットサーフィンもほぼしません。情報収集のスタンスでいうと、海外の通信社が発信するニュースなどを見るくらいですね。ワイドショー的な扇情的なニュースは無視しています。個人が注視すべきことは、視聴率やPV数に左右されるような情報の中にはないと思うのです。世の中を動かす源流にあるのは、個別の事象ではなく、自然のなすことや、世界各国の政治的な動向等です。
市民は社会の制度や行政の仕組みを監視したほうがいいということでしょうか?
そうかもしれません。とはいえ、みんな目の前の自分の生活に手一杯で、どこまでその監視の目が機能するかは分かりません。少なくとも余裕のある人は、社会の制度や行政の仕組みの現状を見ていったほうがいいのかもしれませんね。
共生社会を実現するためにどのようなことが必要でしょうか。
共生の反対が対立だとすると、それを防ぐ方法を考えることも共生社会をつくる一手になるのではないかと思います。対立が起こる根底には「恐怖心」があります。たとえば、人生の充実度が高い人は、むやみやたらと他者と対立しないわけです。それはそうですよね、自分の歩んでいる道が脅かされていないのですから。反対に、なにか不足感を覚えていたり、自分の生活や領域になにかが恐怖を及ぼす可能性があったりするときに、対立は生まれます。言語や文化の違いも同じです。自分が知らない領域だからこそ、自分を守るために攻撃したくなるのです。それだって、理解さえすれば恐怖の対象ではなくなります。恐怖を恐怖のままで固めてしまわず、まずはそこに一歩でも寄ってみて知ることで、恐怖の芽を摘んでいくことが大切ではないでしょうか。
共生社会というまちづくりを進める行政に対していうのであれば、まちのこれからの在り方をきちんと予測するべきだと思います。これだけ人口減少が予想されている中で、所有権が無数に分散した大規模な建物をたくさん建てても、いずれゴーストタウンのような廃墟だらけになりませんか。現在の法制度ですと、たとえばマンションの建て替えには所有者の5分の4以上の賛成が必要とされていますが、築数十年経った建物でそれをやるのはほぼ無理ですよね。容積率の緩和により、デベロッパーの資金で古いマンションを容積率めいっぱいまで部屋数を増やしながら建て替える、なんていうスキームも、近年以降建った建物にはもう使えないわけです。大規模修繕だって難易度が高い。建て替えが難しい建物を建てて、その後のまちはどうなるのか今一度考えた方がいいですよね。民間企業の建てるものに対しても、まちとして長期的なまちづくりを考えるのであれば、ある程度コントロールする必要があるのではないかと思います。本当か分かりませんが、全世界の人口は琵琶湖に収まる、と聞いたことがあります。世界的にも住む場所はそれほど必要ないのではないかと思いますし、江戸川区なんかは、下町的な町並みの面白さを残すためにも、なるべく既存の建物の耐震性強化等でどうにかする道を模索した方がいいのではないでしょうか。

自分にとって未開の経験から得ること
羽田さんが今後挑戦してみたいことがあれば教えてください。
自分にとっての“辺境”を探したいです。楽しさは自分の知らないことの中にあるように思います。自分の価値観や感覚が揺らぐようなことに身を投じることは大事になってくるはずです。それは、知らない場所に実際にいくことや、知らなかったことに挑戦すること、知らない文化を知ることかもしれません。自分の中でどこか不自由さを感じる“辺境”に積極的に迷いにいってみたいです。そこで見えてくることや出会えるものには非常に興味があります。
プロフィール

羽田圭介(はだ けいすけ)
東京都出身、1985年生まれ。高校在学中に小説「黒冷水」で文藝賞を受賞し、小説家デビュー。
2015年「スクラップ・アンド・ビルド」で芥川賞を受賞。その他にも『走ル』『盗まれた顔』『メタモルフォシス』『成功者K』『ポルシェ太郎』『Phantom』『滅私』『タブー・トラック』『バックミラー』などの小説や、『羽田圭介、クルマを買う。』『三十代の初体験』『羽田圭介、家を買う。』などエッセイも出版。


